
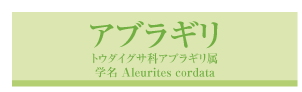
●雌雄同株
●分布:本州(中部以西)、四国、九州の山地
●葉:長さ20cmにもなり、普通3裂し、裏面は多少粉白色
●花:枝の先に白色の花が円錐状に集まって咲く
●果実:殻に包まれ、中に3個の大きな種子がある
●中国原産で古くに渡来
●油を採るために各地で栽培されていたが、今では各地で自生している。
| ●【植物編 木本】Top |  |
|||||||||
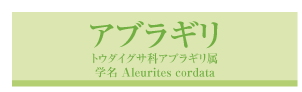 |
||||||||||
| 観察時期 | ||||||||||
| 6月頃(花期) | ||||||||||
| 形態・分布・生態的特徴等 | ||||||||||
| ●落葉高木 ●雌雄同株 ●分布:本州(中部以西)、四国、九州の山地 ●葉:長さ20cmにもなり、普通3裂し、裏面は多少粉白色 ●花:枝の先に白色の花が円錐状に集まって咲く ●果実:殻に包まれ、中に3個の大きな種子がある ●中国原産で古くに渡来 ●油を採るために各地で栽培されていたが、今では各地で自生している。 |
||||||||||
| へぇ〜、そうなん! 〜なるほど豆知識〜 | ||||||||||
| 種子から絞った油は桐油と呼ばれ、かつては油紙、和傘、雨合羽、灯油など広く使われていましたが、ビニールなどの登場でその用途が激減しました。京都、福井などでは「ころび(桐実)」と呼ばれ、かつては米一俵と桐実一俵が同じ値で取引され、農家の貴重な現金収入でした。丹後地方はその一大産地であったと言います。また、その木炭は漆器の研磨に適しているので、炭に焼かれ減少していると言いますが、大浦(おおうら)半島にはまだかなり残っています。和名は、桐に似て油を採ることからつきました。油は有毒なので食用にはなりません。 | ||||||||||