
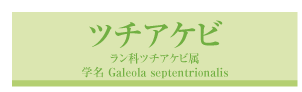
●多年草
●分布:全国各地の山地の木陰に稀に生える
●葉:まばらに鱗片葉をつけるが、緑色の葉はない
●花:6〜7月に黄褐色の半開きの花をたくさん咲かせる
●果実:バナナ状で長さ6〜10cm、径は約3cmで赤く熟し異彩を放つ
●根茎は太く横にはい、地上茎は肉質でかたく黄褐色をしている
●腐生蘭(ふせいらん)で菌類と共生して栄養を得ている。
※文中の下線付き文字をクリックして詳しい情報をご覧ください。
| ●【植物編 草本】Top |  |
|||||||||
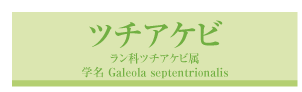 |
||||||||||
| 観察時期 | ||||||||||
| 9〜11月頃(結実期) | ||||||||||
| 形態・分布・生態的特徴等 | ||||||||||
| ●日本固有種 ●多年草 ●分布:全国各地の山地の木陰に稀に生える ●葉:まばらに鱗片葉をつけるが、緑色の葉はない ●花:6〜7月に黄褐色の半開きの花をたくさん咲かせる ●果実:バナナ状で長さ6〜10cm、径は約3cmで赤く熟し異彩を放つ ●根茎は太く横にはい、地上茎は肉質でかたく黄褐色をしている ●腐生蘭(ふせいらん)で菌類と共生して栄養を得ている。 |
||||||||||
| へぇ〜、そうなん! 〜なるほど豆知識〜 | ||||||||||
| 和名の由来は「土に生えてアケビのような実をつける」ことにちなんでいます。また、「山伏の錫杖(しゃくじょう)」に似ていることから別名を「ヤマノカミノシャクジョウ」とも言います。漢方では果実を生薬名「土通草」(どつうそう)と呼び、強壮の薬として用いられています。6月下旬〜7月上旬に多祢山(たねやま)に登るとこの花を見ることができるかもしれません。
※文中の下線付き文字をクリックして詳しい情報をご覧ください。 |
||||||||||