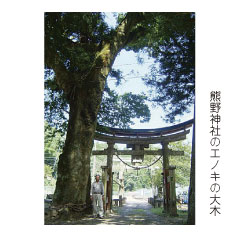
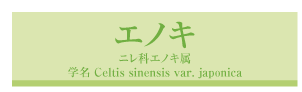
●雌雄同株
●分布:本州・四国・九州の山野
●葉:長さ5〜9cmで、上半分に鋸歯(きょし)がある。葉面はざらつき、3本の脈が目立つ。互生
●花:4〜5月頃に淡黄色の花を咲かせる
●果実:小さな球形の実をつけ、9月頃に赤褐色に熟し、小鳥が集まる
●オオムラサキやゴマダラチョウの食草。
※文中の下線付き文字をクリックして詳しい情報をご覧ください。
| ●【植物編 木本】Top | 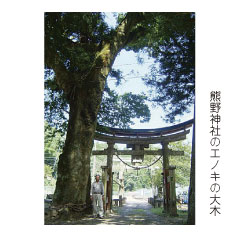 |
|||||||||
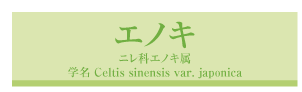 |
||||||||||
| 観察時期 | ||||||||||
| 通年 | ||||||||||
| 形態・分布・生態的特徴等 | ||||||||||
| ●落葉高木 ●雌雄同株 ●分布:本州・四国・九州の山野 ●葉:長さ5〜9cmで、上半分に鋸歯(きょし)がある。葉面はざらつき、3本の脈が目立つ。互生 ●花:4〜5月頃に淡黄色の花を咲かせる ●果実:小さな球形の実をつけ、9月頃に赤褐色に熟し、小鳥が集まる ●オオムラサキやゴマダラチョウの食草。 |
||||||||||
| へぇ〜、そうなん! 〜なるほど豆知識〜 | ||||||||||
| 古くから村境や祠などの脇に植えられ、江戸時代には街道整備に際し、一里塚の指標として植えられました。このためか、この木は人里に多く見られます。エノキは「縁の木」に通じ、縁結び・縁切りの木とされ、木に願をかけ、葉や皮を飲むと願いが叶うと言われてきました。和名は、1.枝が多い木(エノキ)、2.よく燃えることから燃え木(モエキ)など諸説がありますが、はっきりとはわかりません。与保呂(よほろ)地区の日尾池姫(ひおいけひめ)神社、久田美(くたみ)地区の熊野(くまの)神社には直径1mを越す大木があります。
※文中の下線付き文字をクリックして詳しい情報をご覧ください。 |
||||||||||