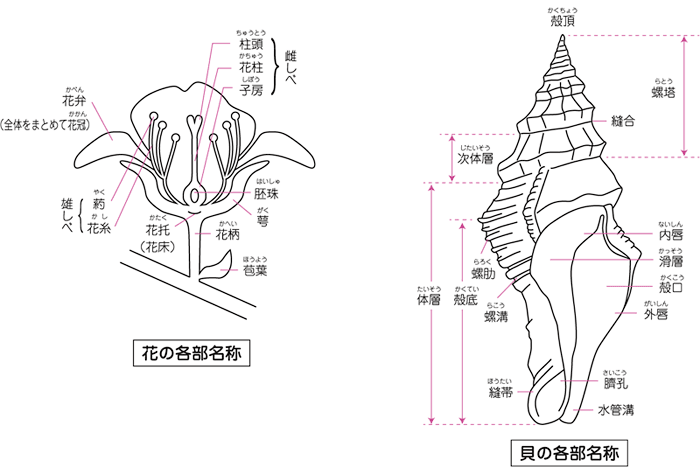用語解説
| 安山岩 (あんざんがん) |
火山岩の一種。 斜長石(しゃちょうせき)・輝石(きせき)・角閃石(かくせんせき)などの鉱物からなり、黒雲母(くろうんも)を含むこともある。 | |
| 魚付林 (うおつきりん) |
魚介類の生息、育成に好影響をもたらす森林。海岸部に存在する森林ばかりでなく、河川上流部の森林も広い意味で魚付林と言われている。 | |
| 羽 脱 (うだつ) |
樹木等で成長した幼虫が羽化し、成虫がその樹木等から自力で脱出すること。 | |
| 羽 片 (うへん) |
羽状複葉(うじょうふくよう:主脈の左右に小葉が羽状に並んでいる葉の形状)の葉で、軸についた小葉の一片。 | |
| 越年草 (えつねんそう) |
一年性植物のうち、秋に発芽して冬を越し、春に開花結実して枯死(こし)するもの。 | |
| 追 星 (おいぼし) |
魚類の生殖期に、雄の頭部やひれに現れる多くの白い円錐(えんすい)形の小突起。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 塊 茎 (かいけい) |
地中にある茎〔地下茎〕の一部がデンプンなどの養分を蓄え、塊状に肥大したもの。 | |
| 花 冠 (かかん) |
一つの花の花弁(かべん)〔花びら〕全体をまとめた呼び名。 | |
| 過眼線 (かがんせん) |
鳥の顔の、くちばしの基部から眼の前後を通る線状の模様。 | |
| 核 果 (かくか) |
液果(えきか)〔成熟後も水分を多くもっている果実〕の一種。外果皮(がいかひ)は薄く、多肉質で水分の多い中果皮(ちゅうかひ)と、厚く堅い内果皮(ないかひ)とをもつ果実。 | |
| 角閃岩 (かくせんがん) |
角閃石(かくせんせき)と斜長石(しゃちょうせき)から構成される結晶質の岩石。 | |
| 萼 片 (がくへん) |
萼(がく)〔花の最も外側の部分。多くは緑色であり、つぼみのときは内部を包み保護する。〕を形成する各々の裂片(れっぺん)。 | |
| 花崗岩 (かこうがん) |
深成岩のひとつ。流紋岩(りゅうもんがん)とほぼ同じ化学組成をもち、完晶質(かんしょうしつ)・等粒状(とうりゅうじょう)で石英(せきえい)・雲母(うんも)・長石(ちょうせき)などから成る。色は純白ないし淡灰色。磨くと光沢が出る。 | |
| 風 切 (かざきり) |
鳥類の翼の骨格に直接付着している堅い羽の集合。翼の後縁を形成し、飛翔に重要な働きをする。 | |
| 花 序 (かじょ) |
植物の花の付き方(配列)のこと。花軸の下位から上位へと順次開花する無限花序と、主軸の頂端から下位へと開花していく有限花序に大別される。 | |
| 花 穂 (かすい) |
穂のような形で咲く花のこと。 | |
| 果 穂 (かすい) |
穂のような形で小さな果実が多数集まったもの。 | |
| 河跡湖 (かぜきこ) |
蛇行する河川の流路が変わることで、もとの河川の一部が取り残されてできた湖。 | |
| 花 柱 (かちゅう) |
雌しべの一部で、柱頭(ちゅうとう)と子房(しぼう)との間の円柱状の部分。柱頭(ちゅうとう)についた花粉からこの中に花粉管が伸び、受精する。 | |
| 滑層歯 (かっそうば) |
滑層〔殻口内唇(かくこうないしん)や、種によっては螺塔(らとう)にも被覆(ひふく)するエナメル質のような物質〕が厚く発達し形成したもの。 | |
| 花被片 (かひへん) |
花被(かひ)〔萼(がく)と花びらの総称〕を構成する花葉の1枚1枚のこと。 | |
| 冠 羽 (かんう) |
鳥の頭にあって,周りより長く伸びた羽毛。 | |
| 崖錘堆積物 (がんすいたいせきぶつ) |
急傾斜の山麓(さんろく)に風化した岩石片が滑り落ちてできた半円錐(えんすい)状の地形の堆積物。 | |
| カンラン岩 (かんらんがん) |
火成岩〔深成岩〕の一種で、超塩基性岩に分類される。主にカンラン石で構成され、一般に輝石(きせき)を伴う。 | |
| キール | カメの背甲(はいこう)等に見られる筋状の隆起。 | |
| 聞きなし (ききなし) |
鳥のさえずり・鳴き声を、それに似た言葉に置き換えて聞くこと。 | |
| 偽球茎 (ぎきゅうけい) |
ラン科の植物に見られる、茎が肥大してできる球茎状(きゅうけいじょう)の水分や栄養の貯蔵組織。 | |
| 気 根 (きこん) |
植物の根の形態のひとつ。地上部から空気中に露出した根のこと。空中の湿気を吸収したり、保水や支柱の役割をする等、役割は植物により異なる。 | |
| 距 (きょ) |
萼(がく)や花弁(かべん)の基部にある袋状の突起。中に細長い蜜腺(みつせん)がある。 | |
| 京都府歴史的 自然環境保全地域 (きょうとふれきしてき しぜんかんきょうほぜん ちいき) |
「京都府環境を守り育てる条例」に基づいて指定された保全地域。自然環境が歴史的遺産と一体になって、優れた歴史的風土を形成している地域。 | |
| 棘 条 (きょくじょう) |
魚のひれの、硬いすじ。 | |
| 鋸 歯 (きょし) |
植物の葉や花弁の縁にある、ノコギリの歯のようなぎざぎざの切り込み。 | |
| 華 鬘 (けまん) |
仏堂内陣(ぶつどうないじん)の欄間(らんま)などにかける荘厳具(しょうごんぐ)。金・銅・革などを材料に,花鳥・天女などを透かし彫りにする。 | |
| 後 食 (こうしょく) |
成虫になってからの食事のこと。 | |
| 婚姻色 (こんいんしょく) |
魚類・両生類・は虫類などで、繁殖期に全身や腹面の体色が著しく変化すること。 | |
| 根出葉 (こんしゅつよう) |
地表にきわめて近い部分から密集して出る葉。越年草・多年草にみられ、冬にロゼットとなるものが多い。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 臍 孔 (さいこう) |
巻貝が巻きながら成長していくとき、巻きの中心下側に生じる空所。 | |
| 西国二十九番札所 (さいごくにじゅうくばん ふだしょ) |
近畿2府4県と岐阜県にある三十三箇所の観音霊場(かんのんれいじょう)を西国三十三所と呼び、松尾寺(まつのおでら)はその二十九番札所。 | |
| 蒴 果 (さくか) |
裂果(れっか)〔熟すと果皮の一部が裂けて開き、中の種子を放出する果実〕の一種。二枚以上の心皮(しんぴ)からなる子房で、成熟すると果皮が乾燥し、縦に開裂して種子を出す。 | |
| 砂 州 (さす) |
岬や湾の出口などの海岸の突出部から、細長く突き出るように延(の)びる、砂や小石が堆積してできた地形を砂嘴(さし)といい、砂嘴(さし)がさらにのびて湾の対岸や陸地に接するようになった地形を砂州(さす)という。 | |
| 三倍体 (さんばいたい) |
基本数の3倍の染色体数をもつ生物体。減数分裂ができにくいため、実を結ばないことが多い。 | |
| 示準化石 (しじゅんかせき) |
地層の地質年代を決定する指標となる化石。特定の年代に生存し、地理的分布の広かった生物の化石を指す。 | |
| 耳 腺 (じせん) |
目の後ろから鼓膜の後ろにある細長い隆起。 | |
| 自然堤防 (しぜんていぼう) |
川の両側に自然にできた堤防状の高まり。河水中の土砂が堆積してできる。 | |
| 蛇紋岩 (じゃもんがん) |
暗緑色〜黄緑色で、ヘビの皮のような模様をした岩石。 | |
| 縦 肋 (じゅうろく) |
巻貝で殻頂(かくちょう)を上にして立てたとき、縦方向に走る規則的な隆起。 | |
| 珠 芽 (しゅが) |
腋芽(えきが)〔葉の付け根にできる芽〕が養分を蓄えて球状となったもの。落下して地上で発芽し、無性的に新しい個体となる。 | |
| 繻 子 (しゅす) |
繻子(しゅす)織り〔縦糸と横糸とが交差する点が連続することなく、縦糸または横糸だけが表に現れるような織り方〕にした織物。 | |
| 子 葉 (しよう) |
種子が発芽すると最初に出る葉。 | |
| 小月面 (しょうげつめん) |
二枚貝で、左右の殻を合わせたときに殻頂(かくちょう)の前に見られるくぼみ。 | |
| 照葉樹林 (しょうようじゅりん) |
冬でも落葉しない広葉樹で、葉の表面のクチクラ層〔角質の層〕が発達し光沢の強い深緑色の葉を持つ、樹木に覆われた森林。 | |
| 初列雨覆 (しょれつあまおおい) |
鳥の翼の、 風切(かざき)り羽の根元を覆っている羽毛を雨覆(あまおおい)と呼び、そのうち、初列雨覆(しょれつあまおおい)は初列風切(しょれつかざきり)を覆うもの。 | |
| シルト | 砂と粘土との中間の大きさをもつ砕屑物(さいせきぶつ)〔岩石が壊れてできた破片や粒子〕。 | |
| 軸 歯 (じくし) |
軸唇(じくしん)〔殻口(かくこう)の縁のうち、内唇(ないしん)からその下に続く軸にあたる部分〕にある歯。 | |
| 唇 縁 (しんえん) |
唇部分のふち〔殻の口のふち〕。 | |
| 唇滑層 (しんかっそう) |
唇部分の滑層〔エナメル質のようなすべすべした層〕。 | |
| スイ―ピング | 昆虫を採集するのに、捕虫網(ほちゅうあみ)を横や縦にはらうように使う方法。 | |
| 水琴窟 (すいきんくつ) |
水音を楽しむために、庭園に仕掛けられた装置。 手水鉢(ちょうずばち)の排水口の下に水瓶(みずがめ)などを伏せて埋め、その中にたまった水に、手水(ちょうず)からの水の滴が落ちて、弦を弾くような音が聞こえるようにする。 | |
| 全 縁 (ぜんえん) |
植物の葉のふちが、滑らかで切れ込みや凹凸のないこと。 | |
| 前翅長 (ぜんしちょう) |
蝶の前翅(ぜんし)の付け根から先端までの長さ。 | |
| 占有行動 (せんゆうこうどう) |
一定の空間を自分の縄張りとすること。一定の空間を見渡せるところにとまり、そこに入ってくる他の個体を追飛する。 | |
| せん緑岩 (せんりょくがん) |
深成岩の一種。安山岩とほぼ同じ化学組成を持ち、完晶質(かんしょうしつ)で中粒または粗粒(そりゅう)で、主に斜長石(しゃちょうせき)・角閃石(かくせんせき)から成る。 | |
| 痩 果 (そうか) |
植物の果実の一種。小形で果皮は硬く、熟しても裂開(れっかい)しない。一種子を持つ。 | |
| 草原性 (そうげんせい) |
草地を生息地とする性質。 | |
| 総 状 (そうじょう) |
ふさのような形。 | |
| 装飾花 (そうしょくか) |
雄しべ、雌しべが退化し、花びらや萼(がく)が発達した花。 | |
| 曹長岩 (そうちょうがん) |
ほとんど全部が曹長石(そうちょうせき)からなる、優白質の曹長石閃長岩(そうちょうせきせんちょうがん)または斑岩。 | |
| 総苞・総苞片 (そうほう・そうほうへん) |
花序(かじょ)の基部に多数の包(ほう)が密集したものを総苞(そうほう)と言い、その一つひとつを総苞片(そうほうへん)と呼ぶ。 | |
| 束 生 (そくせい) |
植物の葉・花・茎などが集まり、束のようになっているつき方のこと。 | |
| 疎 林 (そりん) |
木がまばらに生えている林。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 托 葉 (たくよう) |
葉柄(ようへい)の基部付近に生じる葉身(ようしん)とは別の葉状片(ようじょうへん)。双子葉(そうしよう)植物に多く見られる。 | |
| 多年草 (たねんそう) |
2年以上にわたって生存する植物。多年生植物とも言う。樹木はこれに属する。 | |
| 多毛類 (たもうるい) |
多毛綱の環形(かんけい)動物の総称。体は多くの体節に分かれ,各体節にいぼ足があり、剛毛が生える。 | |
| 中生代 (ちゅうせいだい) |
地質時代の区分のうち,古生代と新生代との間の時代。今から約2億5000万年前から約6600万年前までの間。古い方から三畳紀・ジュラ紀・白亜紀に三分される。 | |
| 超塩基性岩 (ちょうえんきせいがん) |
塩基性岩のうち、二酸化ケイ素の含有量が重量で45%以下の火成岩の総称。 | |
| 潮間帯 (ちょうかんたい) |
満潮時は海水に浸され、干潮時は空気にさらされる海岸。 | |
| 頂 生 (ちょうせい) |
茎や枝の先端に花などをつけること。 | |
| 蝶 道 (ちょうどう) |
アゲハチョウなどが持つ、飛翔の際のある決まった道筋。 | |
| 土蜘蛛 (つちぐも) |
大和朝廷に服従しなかった辺境の民などの別称。 | |
| 底 唇 (ていしん) |
外唇(がいしん)の底面側。 | |
| 天蚕糸 (てんさいし) |
ヤママユの繭(まゆ)からとった糸。緑色を帯び光沢があり、強度・伸度ともに大きい。 | |
| 倒披針形 (とうひしんけい) |
披針形(ひしんけい)〔先のとがった、平たくて細長い形〕を逆さにした形。 | |
| 常盤木 (ときわぎ) |
常緑広葉樹林のこと。落葉する時期のない広葉樹からなる森林。 | |
| ドラミング | 動物が鳴き声以外の方法で音をたてる動作。鳥が威嚇(いかく)や求愛のために、翼や尾羽などで音を出す行動。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 鳴 袋 (なきぶくろ) |
鳴嚢(めいのう)のこと。カエルなどの喉または頬(ほお)にある鳴き声を発するための空気袋。 | |
| 軟 条 (なんじょう) |
魚のひれにある軟らかいすじ。節や枝分かれのあることが多い。 | |
| 肉穂花序 (にくすいかじょ) |
太い肉質の中軸の周囲に無柄(むへい)の小花が密生しているもの。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 背側線 (はいそくせん) |
目の後ろに延びる隆起した長い線。 | |
| 背中線 (はいちゅうせん) |
背中の中央部を前後に走る線模様。 | |
| 半低木 (はんていぼく) |
地下や根際で数本の幹に分かれ、主幹が不明瞭で、茎の下半分〜根際のみが木化しているもの。草本と木本の中間的な性質をもつ。 | |
| 斑れい岩 (はんれいがん) |
深成岩のひとつ。玄武岩とほぼ同じ組成をもつ。主に輝石(きせき)と斜長岩(しゃちょうがん)とからなり、カンラン石・角閃岩(かくせんがん)・石英(せきえい)のいずれかを含む。 | |
| ビーティング | 木の枝や草、花などをたたき、その下のネットに昆虫を落として採集する方法。 | |
| 披針形 (ひしんけい) |
先のとがった平たく細長い形。 | |
| ビロード状 (びろーどじょう) |
綿・絹・毛などで織り、表面に毛羽や輪奈(わな)を出した、滑らかで光沢のある織物のような状態。 | |
| 風媒花 (ふうばいか) |
風の媒介によって受粉する花。一般に、花の形や色は単純で、花粉は多量で軽い。 | |
| 複 葉 (ふくよう) |
葉身(ようしん)が二枚以上の小葉よりなる葉の総称。小葉3枚からなる3出複葉、葉柄(ようへい)の先に小葉が放射状につく掌状複葉(しょうじょうふくよう)、中軸の左右に小葉の並ぶ羽状複葉(うじょうふくよう)などがある。 | |
| 仏炎苞 (ぶつえんほう) |
肉穂花序(にくすいかじょ)を包む大形の苞葉(ほうよう)。サトイモ科植物に見られる。 | |
| 吻 (ふん) |
動物の口の付近から、先へ突き出していたり伸縮できたりする部分の総称。 | |
| 閉鎖花 (へいさか) |
花が開かないまま自家受精を行い結実する花。 | |
| 変 異 (へんい) |
同種の生物個体間に形態的・生理的差異が現れること。 | |
| 苞 (ほう) |
芽や蕾(つぼみ)を包み、保護する小形の葉。包葉。 | |
| 放射助 (ほうしゃろく) |
二枚貝で、殻頂(かくちょう)から縁に向かう線状の隆起。 | |
| 紡錘形 (ぼうすいけい) |
円柱状で真ん中が太く、両端がしだいに細くなる形。 | |
| 母 岩 (ぼがん) |
ある貫入岩床(かんにゅうがんしょう)〔マグマが地表に噴出しないで,地下で固結したもの〕や鉱床(こうしょう)などを取り囲んでいる周囲の岩石。 | |
| 保健保安林 (ほけんほあんりん) |
保安林の一種。森林レクリエーションの活動の場として生活にゆとりを提供したり、空気の浄化や騒音の緩和といった生活環境を守る役割などを持つ。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 鳴 嚢 (めいのう) |
カエルなどの喉または頬(ほお)にある、鳴き声を発するための空気袋。 | |
| 木本性 (もくほんせい) |
樹木としての性質。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 葯 (やく) |
雄しべの一部で、花粉をつくる器官。 | |
| 有舌尖頭器 (ゆうぜつせんとうき) |
基部側に突起を持つ槍先形(やりさきがた)の石器。 | |
| 葉 腋 (ようえき) |
植物の葉が茎に付着する部分で、芽ができるところ。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 螺 管 (らかん) |
巻貝の殻は、基本的に一本の管が螺旋状(らせんじょう)に巻いた形状をしており、その管のこと。 | |
| 螺 条 (らじょう) |
螺肋(らろく)の隆起が微弱なもの。 | |
| 螺状縦脈 (らじょうじゅうみゃく) |
縦方向に螺旋状(らせんじょう)に走る規則的な隆起線。 | |
| 螺状彫刻 (らじょうちょうこく) |
貝殻の螺旋(らせん)に平行な凹凸構造。 | |
| 螺 層 (らそう) |
巻貝の巻きの一巻き一巻き。層と略すこともある。 | |
| リアス式海岸 (しきかいがん) |
浸食で多くの谷の刻まれた山地が、地盤の沈降または海面の上昇によって沈水し、複雑に入り組んだ海岸線をなすもの。 | |
| 隆起縁 (りゅうきえん) |
体の断面を見たとき、 尖(とが)っている部分の様子。 | |
| 隆 条 (りゅうじょう) |
カメの背甲(はいこう)等に見られる筋状の隆起。 | |
| 両性花 (りょうせいか) |
一つの花に雄しべと雌しべをもつ花。 | |
| 鱗 茎 (りんけい) |
地下茎の一種。短い茎の周囲に生じた多数の葉が養分を貯えて多肉となり、球形・卵形になったもの。 | |
| 鱗 片 (りんぺん) |
うろこ状の細片のこと。 | |
| 齢幼虫 (れいようちゅう) |
幼虫の成長段階を脱皮回数で表したもので、 孵化(ふか)直後の幼虫を一齢幼虫、1回目の脱皮後の幼虫を二齢幼虫、二回目の脱皮後の幼虫を三齢幼虫という。 | |
| 裂 片 (れっぺん) |
分裂葉(ぶんれつよう)の切れ込みが入った部分のこと。花びらの場合なども裂片(れっぺん)という。 | |
| ロゼット | 葉が地面の表面に接して、短い茎に放射状についている状態。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
| 輪中堤 (わじゅうてい) |
ある特定の区域を洪水から守るために、その周囲を囲むようにつくられた堤防。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ